はじめに
これまで、英語の本を自由自在に読み進める方法について、とても抽象的に書いてきました。
英語の本を読めるようになるため、最初の一冊としておすすめの本については次の記事を参考にしてみてください。
また、大枠として、「英語の本との対話を楽しむ」ことで英語読書ができるようになることについては次の記事で、紹介しています。
今回は、英語読書最初の一冊としておすすめに挙げた本のうち、
Never Let Me Go by Kazuo Ishiguro (カズオ・イシグロ「わたしを離さないで」の英語原書)
の冒頭部分を具体例に、英語の本との対話を楽しむとはどういうことか、説明したいと思います。
【※冒頭部分への言及にとどめ、ネタバレはしないようにしますので、未読の皆様も安心して以下ご覧ください。】
Never Let Me Go は、言わずと知れたカズオ・イシグロの代表作ですが、これを日本語ではなく、英語の原文で読むことによって、カズオ・イシグロの凄さ、なぜ、ノーベル文学賞を受賞したのか、その理由がハッキリとわかってきます。
カズオ・イシグロについて
この記事の本題からはそれてしまいますが、せっかくですので、カズオ・イシグロについて僕の印象を簡単に紹介しておきます。
カズオ・イシグロといえば、1989年に「日の名残り」でブッカー賞を受賞し、英文学界の頂点にたった上、2017年にノーベル文学賞を受賞して世界文学の頂点を極めた、現在有数の文豪であることは論をまたないところです。
まず、特筆すべきは、カズオ・イシグロが日本人(この際国籍はどうでもいいです)であるということです。
6歳の頃にイギリスに移住し、それから英語を身につけているということですが、6歳って相当日本語が出来るようになっていて、物事を日本語で考えるようになっている年頃ですから、当時のイシグロは純然たる日本語ネイティブだったわけです。
つまり、イシグロは、第二言語として、英語を学び、その後、英文学界の頂点にたったということなのです。
インタビューでも、イシグロ自身が、自分の英語に、英語ネイティブのような基礎がないことを認めているということです。
だからなのかはわかりませんが、イシグロの英語は驚くほどシンプルで読みやすいです。語彙も平易で、文章はものすごくわかりやすいです。純粋英語ネイティブの英語作家の文章とはこの点でかなり違いがあるように感じます。
しかし、そのシンプルさにもかかわらず、イシグロの英文は、他の同世代の英語作家を寄せつけない圧倒的な深みを有しています。
イシグロの文章を読むと、そこからは、明らかにイシグロと感じさせる非常にユニークな雰囲気を感じ取ることができ、読者は他の作家からは感じ取ることができない独特の哀愁を感じることになります。
ぜひ、この記事をきっかけに、イシグロ作品の英語に直に触れてみていただきたいと考えています。
Never Let Me Go 冒頭の引用
閑話休題、本題に戻ります。
自由自在に英語読書をするため、英語の本とどのように対話を進めるべきか。
具体例として用いる、Never Let Me Go の冒頭部分を引用します。
England, late 1990s
Part One
Chapter One
My name is Kathy H. I’m thirty-one years old, and I’ve been a carer now for over eleven years. That sounds long enough, I know, but actually they want me to go on for another eight months, until the end of this year. That’ll make it almost exactly twelve years. Now I know my being a carer so long isn’t necessarily because they think I’m fantastic at what I do. There are some really good carers who’ve been told to stop after two or three years. And I can think of one carer at least who went on for all of fourteen years despite being a complete waste of space. So I’m not trying to boast. But then I do know for a fact they’ve been pleased with my work, and by and large, I have too. My donors have always tended to do much better than expected. Their recovery times have been impressive, and hardly any of them have been classified as ‘agitated’, even before fourth donation. Okay, maybe I am boasting now. But it means a lot to me, being able to do my work well, especially that bit about my donors staying ‘calm’. I’ve developed a kind of instinct around donors. I know when to hang around and comfort them, when to leave them to themselves; when to listen to everything they have to say, and when just to shrug and tell them to snap out of it.
場所・年代、第一部、第一章のタイトルがあって、第一段落。
これが、Never Let Me Go 冒頭の構造になっています。
実は、この第一段落、僕が、これまで読んだあらゆる本の中で、最も優れた第一段落なのではないかと考えています。間違いなく、現代英文学を代表する名文です。
ぜひ、この記事をきっかけに、英語読書を楽しむのはもちろんですが、Never Let Me Go のすばらしさに気が付き、全文を英語で読破するきっかけとしていただきたいと考えています。
これがどれほどの名文であるかは、一つずつ対話を重ねていけば明らかとなっていきます。
場所・年代との対話
England, late 1990s
まず、読者は、Never Let Me Go を読み始めるとすぐに、この一行だけが記載されたページを目にすることになります。
これは、この小説の舞台となる場所と年代が記載されていると考えるのが自然です。そのため、僕は、ここから、
「イングランドが舞台で、1990年代後半の物語なのか。架空の世界を舞台にした小説ではなく現実世界を舞台にした小説なんだな、大昔の出来事に関する歴史小説ではなく、現代を舞台にした小説なんだな」
という反応をしました。このような先入観を植え付けられたといってもいいかもしれません。
実は、すでに、この場所と年代を示す3単語に、イシグロの壮大な仕掛けが仕組まれており、わずか3単語で、僕はイシグロワールドに引きずり込まれることになっていたのです。
ただ、この対話に、英語力は一切関係ないですよね。
語り手の名前との対話
次に、第一章第一段落第1文です。
My name is Kathy H.
これ以上ない簡単な英文ではないでしょうか。
このように、Never Let Me Goは、尋常ではなくシンプルな英文から始まります。英語として意味が分からなかった方はいないでしょう。
ところが、この超絶シンプルな、意味の間違いようがない英文が、すでに、対話の相手として恐るべき深みをもっているのです。
まず、この小説がKathy Hによる一人称小説であることがわかりました。また、Kathyは女性のファーストネームのように思え、女性の視点からの一人称小説ではないかと読めるのです。ところが、直ちに疑問がわいてきます。
「H」って何?
英語圏の名前って、ふつうは、ファーストネームを省略して大文字で表記し、ファミリーネームはフルで表記しますよね。J・K・ローリング、C・S・ルイス、J・R・R・トールキンなどなど。
Kathyは明らかに女性のファーストネームです。では、彼女のファミリーネームは?「H」はファミリーネームを省略したもの?ファミリーネームを省略するってどういうこと?
メチャクチャシンプルな第1文と対話しただけで、これだけの疑問を本に対して投げかけることになります。
そうすると、このシンプルを極めた一文だけで、すでに、Never Let Me Goの読書が楽しくワクワクするものになってきたのではないでしょうか。
年齢・経歴との対話
しかし、イシグロの英文のもつ恐ろしさは、まだまだこれからです。第2文と対話してみましょう。
I’m thirty-one years old, and I’ve been a carer now for over eleven years.
これまた、超絶簡単な英文です。僕たち日本人が英語で自己紹介するときも簡単に頭に浮かびそうな文章ではないでしょうか。
Kathy は31歳で、どうやら「a carer」という職業で、11年以上の経験があるんだなということがわかります。
ここから、僕は次のように対話を進めました。
「31歳といえば社会人としては比較的若いな。ただ、すでに a carerとして11年以上の経験となると、20歳で就職したのか。就職した時期は結構早いな。まあ、でも、特定の職業で11年ていうのは、まだまだ若手か、中堅になりたてくらいのものでベテランというにはほど遠いよな…」
語り手からの意外な反応
ところが、第3文は予想外の反応を読者に返してくるのです。
That sounds long enough, I know, but actually they want me to go on for another eight months, until the end of this year.
この第3文も英語として難しい語彙・文法は一切なく、スッと意味は理解できたのではないでしょうか。
しかし、読者の疑問に対する反応としては意外な内容となっています。
語り手であるKathy自身は自分の11年の経歴を「長い」と評価しています。ここで、僕の感覚とKathyの感覚に大きなずれが生じています。
31歳の社会人が11年の経歴を「十分に長い」と評価することに、僕は、違和感を禁じえません。会社員にしろ事業主にしろ、およそプロを名乗る職業の場合、11年程度では、少なくとも、長いと評価されるものではないように感じるのです。
もちろん、ある経歴を長いと評価するか短いと評価するかは、その内容によって、相対的に決まる問題であり、あまり長続きしないと思われる仕事内容であれば、11年だと長いと言われる職種もあるとは思います。
そうすると、Kathy Hの周りには、同じ経歴で10年以上継続した人がたくさんはいないということでしょうか。
次に、唐突に「they」が出てきます。すでに第一文でこの小説が一人称視点で語られていることがわかりました。
小説を読む場合、その視点をまずはっきりさせることが重要です。
特に一人称小説の場合は、視点となる人物が「誰に」話しかけているのかを意識することは非常に重要です。
広く一般読者に語り掛けている場合は、一人称視点からすべての事実が語られることになるのですが、特定の対象に語り掛けている場合、語り手と聞き手の共通認識となる事項については省略が許されることになるからです。
この第3文で唐突に出てきた「they」は語り手と聞き手が共通認識として有している前提事実となる複数の人物と考えられます。
そのため、Kathy Hはいったい誰に語り掛けているのか、「they」とは誰なのかが疑問として浮上してくることになるのです。
いったいこの小説は何なんだ?
対話を重ねるにつれ次々に浮かび上がる疑問、違和感により、はやく続きを読みたい、先が気になる!という気持ちになってきたのではないでしょうか。
とりあえずのまとめ
ここまで、英語読書における対話の具体例として、Never Let Me Go 冒頭の、場所・年代に関する指摘、第一段落の第1文から第3文までとの対話例を示してみました。
読み進めるのに英語力が全く関係ないということはおわかりいただけたでしょうか。
そのうえで、シンプルで読みやすい英語であるにもかかわらず、対話の相手として、イシグロの文章がいかに骨太であるかも体感いただけたと思います。
英文との対話を積み重ねていけば、内容そのものが気になって、ワクワクして、英単語だの英文法だのといった些末な問題はすぐに雲散霧消します。
この第一段落の凄さはまだまだ続きますので、その過程をさらに、記事を改めて紹介できればと考えています。

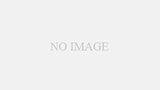
コメント