はじめに
前回の記事はこちら。未読の方は先に、「その1」をご覧いただきたくお願いします。
【※今回の記事でも、冒頭部分への言及にとどめ、ネタバレはしないようにしますので、Never Let Me Go 未読の皆様も安心して以下ご覧ください。】
前回、Never Let Me Go の冒頭、第一段落第3文までを例に、具体的な対話例を示し、読書が対話であること、対話することで読書が楽しくなっていくことをお話ししました。
Never Let Me Go を具体例にしたのは、冒頭が、シンプルな英語が圧倒的名文に仕上がっているからで、ネタバレなく、英語読書における対話の楽しさをお伝えすることができると考えたからです。
すでに前回の記事でその一端を示すことができたのではないかと思っています。
しかし、カズオ・イシグロの凄さは、まだまだ、これからです。
Never Let Me Go 冒頭第一段落の引用
今回の記事でも、具体例として用いる、Never Let Me Go 第一段落を再度引用します。
青いマーカー部分は、前回の記事で引用した部分です。
今回は、もう少し、まとまったかたまりごとに、本と対話するということがどういうことか、具体例を示して行きたいと思います。
My name is Kathy H. I’m thirty-one years old, and I’ve been a carer now for over eleven years. That sounds long enough, I know, but actually they want me to go on for another eight months, until the end of this year. That’ll make it almost exactly twelve years. Now I know my being a carer so long isn’t necessarily because they think I’m fantastic at what I do. There are some really good carers who’ve been told to stop after two or three years. And I can think of one carer at least who went on for all of fourteen years despite being a complete waste of space. So I’m not trying to boast. But then I do know for a fact they’ve been pleased with my work, and by and large, I have too. My donors have always tended to do much better than expected. Their recovery times have been impressive, and hardly any of them have been classified as ‘agitated’, even before fourth donation. Okay, maybe I am boasting now. But it means a lot to me, being able to do my work well, especially that bit about my donors staying ‘calm’. I’ve developed a kind of instinct around donors. I know when to hang around and comfort them, when to leave them to themselves; when to listen to everything they have to say, and when just to shrug and tell them to snap out of it.
「a carer」に関する叙述との対話
第4文から第7文まで、語り手であるKathy により、a carer について次のような叙述が展開されます。
That’ll make it almost exactly twelve years. Now I know my being a carer so long isn’t necessarily because they think I’m fantastic at what I do. There are some really good carers who’ve been told to stop after two or three years. And I can think of one carer at least who went on for all of fourteen years despite being a complete waste of space.
この文章も英語としてはまったく難しいポイントはなかったのではないでしょうか。難しい単語は一切使われていませんし、内容を把握することが難しい言い回しもありません。
しかし、対話の相手としては相当違和感にあふれた内容になっています。
まず、「a carer」という単語からは、細かい内容はわかりませんが、誰かの面倒をみる職業なのではないかという感覚が生じます。
そのうえで、Kathyがa carer を11年以上継続しているのは、「they」が、Kathyのやっていることを素晴らしいと考えているという理由ではないようです。
本当に良い carers が2~3年で辞めるよう言われる一方、完全に無駄な場所をとっているだけの one carer が14年も継続しているというのです。
なかなか特殊な職業に思えます。
まず、その仕事を継続するかどうかは「they」(語り手と聞き手の共通認識となる複数の者と思われることは前回の記事を参照してください。)が決めるようです。
また、仕事を継続させるかどうかに、技術や能力の良し悪しは関係ないということでしょうか。
さらに、14年 a carer を続けた者に対するKathyの評価、「a complete waste of space」って、とても酷な言い方ではないでしょうか。長く続けている人に対して「完全にスペースの無駄」なんて、ちょっとひどいですよね。
仮に、ある会社で、定年をとうにすぎているにもかかわらず、長く居座っている人がいて、若い職員が苦々しく思っていたとしても、こんな言い方はしないのではないでしょうか。
わからない部分はとりあえず放っておく
次に第8文及び第9文との対話を進めていきます。
So I’m not trying to boast. But then I do know for a fact they’ve been pleased with my work, and by and large, I have too.
第8文にきて、初めて少し難しい単語が登場しました。「boast」です。そこで、いったん、この単語はなかったものとして放っておきます。
第9文を読んで、a carer について継続するかどうかの決定権を有すると思われる「they」も、語り手である Kathy も、Kathy の仕事についてポジティブに捉えていることがうかがわれます。そうすると、第8文もポジティブな内容ではないかと考えることができます。
「a carer」の対象についての対話
第10文及び第11文との対話に進みます。
My donors have always tended to do much better than expected. Their recovery times have been impressive, and hardly any of them have been classified as ‘agitated’, even before fourth donation.
いよいよ、冒頭第一段落の核心的な内容が語られてきました。もともと、a carer という単語から、それが誰かの面倒をみる仕事と感じられていましたが、その対象が「My donors」という表現により絞られたのです。
また、「even before fourth donation」という表現から、donors は何回か donation をする人たちなのかと思えてきます。
さて、ここで、donation は、「寄付」という意味の英単語で、英語読書においては頻繁に出てくる単語です。
そして、英語図書において、donation が用いられる場合、その寄付の対象は、僕の読書経験上、例外なく、お金か、金目の物(美術品・骨董品等)です。
ためしに、Google翻訳で donation を調べてみます。そうすると、英語辞書で次のような説明がなされていることがわかります。
something that is given to a charity, especially a sum of money.
次に、donor についても調べてみると、donationをする人という意味であり、
a person who donates something, especially money to a fund or charity.
となっており、直感的なイメージは、お金を寄付する人なのです。
そうすると、読者としては、a carer が面倒をみる対象である donors という表現から、「お金をたくさん持っている人たちなのかな?」「何回かお金を寄付するのかな?」という疑問を抱くことになるのです。
ただ、お金を寄付する人について、recovery とか、 ‘agitated’ という表現はどうもしっくりきません。「なぜ、お金を寄付する人に、回復が関係するのだろうか?困惑することがある?」という疑問が生じるのです。そこから、「嫌々寄付をやらされているのか?」などといった対話をすすめることになるのです。
知りたいという感情にしたがって調べる
第12文及び第13文との対話を進めます。
Okay, maybe I am boasting now. But it means a lot to me, being able to do my work well, especially that bit about my donors staying ‘calm’.
先ほど、少し難しいといった「boast」が再度出てきました。そのうえで、Kathy にとって、a carer としての仕事がうまくできていること、「my donors」を平穏(calm)な状態にしておくことに大きな意味があるというのです。そこからは、Kathy が自分の仕事に相当ポジティブな感情を有しているように感じられます。
そうすると、「boast」が相当気になってきたのではないでしょうか。この段落に表現されている Kathy の感情、a carerとしての仕事に対する自分自身の評価を読み取るうえで重要な意味を有していそうで、どうしても知りたいと思えるようになるからです。
このような感情が生じた場合にのみ、素直にその感情にしたがって、単語の意味を調べればいいのです。そうすれば、単語を調べること自体が、本との対話の一環として、非常に楽しいものになるからです。
実際にGoogle翻訳の英語辞書で調べてみます。
talk with excessive pride and self-satisfaction about one’s achievements, possessions, or abilities.
日本語では「自慢する」となるでしょうか。
「boast」の意味がわかると、第一段落は、全体的に、前向きな明るい雰囲気の段落に感じれれてくるのではないでしょうか。
Kathy は自分の経歴をポジティブにとらえており、自慢しようとしているわけではないと言いつつ、やっぱり自慢していると言っているわけです。
とてもポジティブな段落という印象を受け、読者としては、これからどんなポジティブな話がなされるのだろうと期待してしまいます。
僕が第一段落を名文と評価する理由
第1段落の最後、第14文及び第15文と対話してみます。
I’ve developed a kind of instinct around donors. I know when to hang around and comfort them, when to leave them to themselves; when to listen to everything they have to say, and when just to shrug and tell them to snap out of it.
Kathyが自分の能力について自慢しているように読めます。しかも、ここで自慢されている能力は、だれかの面倒をみる、だれかを落ち着かせる仕事をするための能力としてはとても重要な能力であるように思えます。
そのため、この第一段落は、ポジティブに自分の a carer としての経歴、能力を自慢している段落であると読むことができ、読者としては、さて、今後、どんな明るい話が今後展開されるのだろうという方向で、本との対話に期待を膨らませることになるのです。
しかし、読者は後に、これが、とんでもないことであったと思い知ることになります。
しかも驚くべきことに、とんでもないことが判明し、この本を読み終えた後に改めてこの第一段落を読み直しても、実は、これまで対話を重ねてきた内容が、まったくおかしくなかったことがわかるのです。
そのうえ、さらに恐ろしいことに、Never Let Me Go を最後まで読み通した後、再度、この第一段落を読むと、とても腑に落ちることが多数あるのです。
カズオ・イシグロは、この第一段落を相当綿密に構成したと考えられます。まさに、マスターワークといっていいのではないでしょうか。
皆様もぜひ、このまま、Never Let Me Go との対話を続け、全文を読破していただければと思います。
まとめ
以上、英語読書における対話の具体例として、前回の記事から2回にわたって、Never Let Me Go 冒頭における本との対話の例を示してきました。
そこには、一切英語力が関係ないことがお判りいただけたのではないでしょうか。
カズオ・イシグロの英文のシンプルさ、読みやすさも相まって、英単語だの英文法だのを気にする必要はなかったと思います。
それでも、たしかに、多少難しい単語が出てくることはあります。
しかし、そのような場合も、本との対話のなかで、どうしても知りたいという感情が生じた際に、それを調べるのであれば、その調べる過程そのものが楽しくワクワクするものであることがお判りいただけたのではないでしょうか。
実際、上記の「boast」は、あえて覚えようとするまでもなく、上記第一段落の重要な単語として、勝手に記憶に定着したのではないでしょうか。
このように定着した単語は、単なる無味乾燥な文脈を離れた文字の羅列ではなく、Kathyの感情を示す文脈のなかで、生きた物語の一部として記憶に定着したはずです。
それよりも何よりも、とにかく、Never Let Me Go の中身の凄さを前に、英語力などといった問題がいかに些末であり、そのようなことにかまけて英語読書を後回しにしている時間はなく、とにかく本との対話に飛び込んでいかなければならないことを感じていただけたらこれにまさる喜びはありません。
ぜひ、一刻も早く、自分の読みたいと思う本の世界に飛び込んでいただきたいと思います。

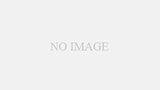
コメント